
愛犬の皮膚がベタつく、カサカサしてフケっぽいと感じたら、それは「脂漏症(しろうしょう)」という皮膚病の可能性があります。
わが家の愛犬「にこまる」も、長い間この「脂漏症」に悩まされています。
犬の脂漏症は強いかゆみを伴うので、にこまるも爪で皮膚を掻きむしってしまい、出血してしまうことも度々です(泣)
その傷が膿んで炎症を起こし、膿皮症にもなってしまいました。
そのため毎日の肌チェックや健康管理が大切になります。
目次
犬の脂漏症で起こる主な症状
愛犬に以下のような症状が見られたら、脂漏症かもしれません。
-
肌や毛がベタつく
-
体臭がきつくなる
-
フケの量が異常に増える
-
脱毛症状や発疹が見られる
-
体の広範囲に皮膚炎が見られる
-
かさぶたが剥がれたようなものが出る
-
1cm未満のでこぼことした湿疹が現れる
犬の脂漏症2つのタイプ
犬の脂漏症には2つのタイプがあります。
いずれも脂漏症なので、愛犬に思い当たる症状があったら脂漏症を疑ってみる必要があります。
1. 油性脂漏症

皮膚や毛が脂っぽくベタつき、臭いもきつくなります。
皮膚から皮脂が過剰に出ているからです。
毛が抜けたりフケが落ちたりもします。

2. 乾性脂漏症
逆に乾性脂漏症は、皮脂が少なく乾燥して肌がカサつきます。
抜け毛は少ないのですが、毛ツヤが悪くなります。
油性と乾性、どちらの脂漏症もフケやカサブタのようなものが多く出てきます。
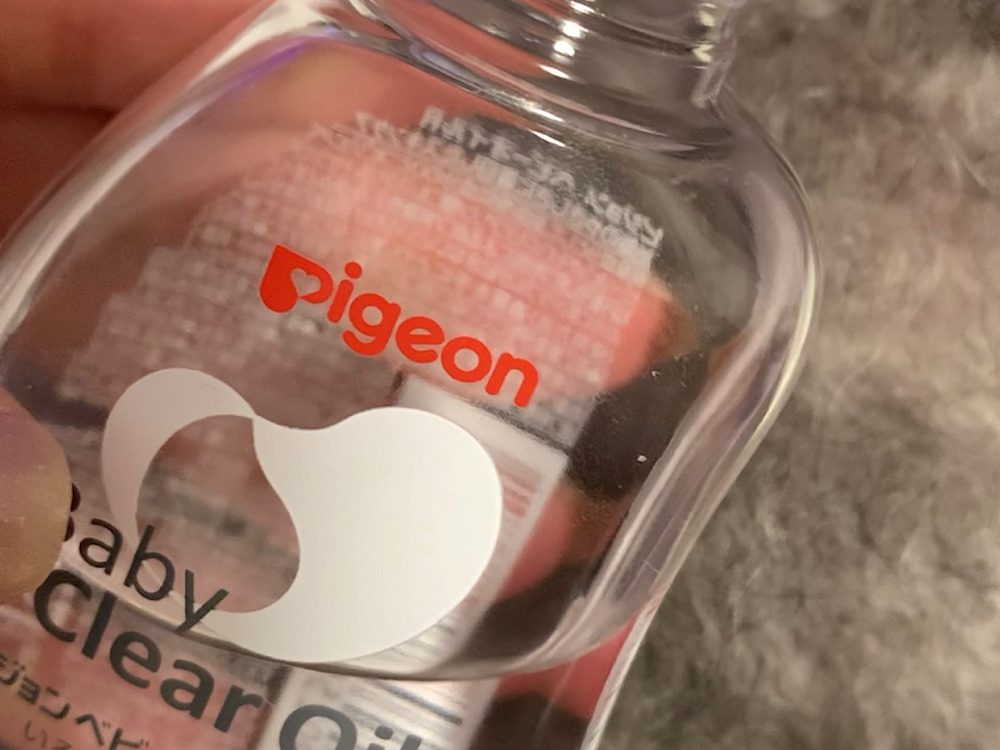
また、毛の根本にカサブタで固まったような塊が現れることもありますが、綿棒にベビーオイルをつけ、この塊に塗り込むように擦ると取ることができます。

犬の脂漏症が起こる2つの要因とマラセチア性皮膚炎
脂漏症の原因には、体質から起こる遺伝的な要因と生活習慣などから起こる後天的な要因があります。
それぞれについて見ていきましょう。
1. 遺伝的要因
シーズーやプードル、ラブラドールなどの犬種は、元々脂漏症になりやすい体質を持っています。
「生まれつき」が原因ですので、完治させることが難しいのです。
そのため「脂漏症との付き合い方」に取り組む必要があります。
2. 後天的な要因
皮膚環境の悪化により、脂漏症になってしまうことがあります。
その原因として、誤ったスキンケアや偏食、アレルギーやホルモン異常などが挙げられます。
脂漏症の改善に取り組む前に、愛犬の食事や生活習慣、暮らしている環境などを見直す必要があるかもしれません。
3.マラセチア性皮膚炎
脂漏症によって痒みが出るのは、マラセチアという菌が関係しているからです。
マラセチアは、犬の皮膚に元々存在する菌(カビの一種)なのですが、脂漏症で分泌される皮脂がマラセチアのエサになってしまうのです。
そのため、マラセチアが異常繁殖すると炎症を起こし、強い痒みや赤みを生じさせてしまいます。
脂漏症対策は、マラセチア対策でもあります。
愛犬が脂漏症になってしまった時の治療法、対処法は?
愛犬が脂漏症になってしまった場合、以下のような治療法や対処法があります。
-
薬用シャンプーを使う
-
愛犬の食事に気を付ける
-
薬による治療
-
生活環境を整える
-
基礎疾患への対応
それぞれについて見ていきましょう。
1. 薬用シャンプーを使う
犬の脂漏症に対するスキンケアの基本はシャンプーです。
シャンプーによってマラセチア菌の増殖を防ぎ、減らすことができます。
しかし脂漏症に対応したシャンプーは、脂を落とす作用が強く、必要な皮脂膜まで洗い流してしまうことがあります。
犬の皮膚はとてもデリケートなので、皮膚バリアの機能を弱らせないよう、保湿剤などを使用することが重要です。
セラミドなどが配合されたものや、気軽に使えるスプレータイプのコンディショナーなど、様々なものがありますので、愛犬に合ったものを選んであげましょう。
またドライヤーのかけすぎは、かえって皮脂の分泌を刺激して、脂漏症を悪化させることがあります。
ドライヤーを使用する場合は冷風にするか、温風の場合はできるだけ皮膚から離して使用しましょう。
ちなみに「にこまる」は、タオルだけで自然乾燥させることも多いです。
2. 愛犬の食事に気を付ける
太った体型は皮脂の過剰分泌を招き、脂漏症を悪化させることがあります。
特に夏場は蒸れることが多く、脂漏症で苦労することが多くなります。
太りすぎの場合、食事管理でダイエットをしてみては?
3. 薬による治療(飲み薬)
お薬を飲ませることで全身に効果があります。
ただし適切な用法や用量などを守らないと、耐性菌を作り出してしまい、治療が困難になることもあるので、かかりつけの獣医師の指示に従ってください。
4. 生活環境を整える
犬の脂漏症は、高温多湿で悪化します。
梅雨時や夏場は、クーラーや除湿機で温度と湿度を管理してあげましょう。
冬場は、暖房が効きすぎていると皮膚が乾燥し、かえって症状が悪化することがあるので要注意です。
5. 基礎疾患への対応
皮膚のターンオーバー(新陳代謝)がうまくいかない理由の一つとして、基礎疾患が関係している場合があります。
例えば、アトピー性皮膚炎やホルモンの異常などです。
このような場合は、基礎疾患に対処することで、脂漏症の管理もしやすくなることがあります。
こちらもお医者さんの指導を受けることをおすすめします。
ママとにこまるの脂漏症対策!
冒頭でご紹介したように、わが家の愛犬「にこまる」も長年、脂漏症と戦ってきました。
私がはじめて脂漏症に気づいたのは、「にこまる」が5歳くらいの時です。
体がベタベタと脂っぽく、特有の臭いがあったので脂漏症と分かりました。
フケやカサブタも頻繁に出るので、できるだけ皮膚のチェックをしています。
毛の根本にできる塊も、見つけ次第ベビーオイルで取り除くようにしています。
夏場など痒みが激しくなる時は、見ていて可哀想になります。
10歳を過ぎたあたりから悪化がひどくなりました。
かゆい場所を爪で掻きむしることも多く、出血することも度々です(涙)
これまで病院でもらった塗り薬も試してきましたが、効果は感じらませんでした。
塗り薬は、すぐに舐めてしまいますし…(笑)
耳の周り、お腹、指の間、目の周り、4本全ての脚、陰部の周りなどをとても痒がるようになったので、シャンプー療法を開始しました。
週に1回の薬用シャンプーです。
さらに、ひば油を数滴入れた「ひば油風呂」や「カモミール風呂」、「どくだみ風呂」などを試したところ効果を実感!
食事も市販のドッグフードから野菜を中心に切り替えた結果、一番悪かった頃に比べれば、とても良くなってきたと思います。
【薬用シャンプーとひば油風呂の動画】
「ひば油」を入れたお風呂で効果を実感!
ひば油というのは、「青森ひば」という樹木から抽出されるオイルです。
100㎏の木からわずかに1㎏しか取れない貴重な油です。
ひば油に含まれているヒノキチオールには、 優れた雑菌・カビ・ダニなどの増殖を抑えてくれる作用があります。
この成分が菌の増殖を防ぎ、皮膚病の悪化を防いでくれるのかもしれません。
にこまるの場合、以前はシャンプー直後から体を掻いていましたが、「ひば油」を使い出してからは、体を掻く回数がかなり減っています。
ひば油風呂には、1週間に一度程度入れています。
ひば油風呂以外の6日間は、1日1回、ひば油を入れた水を体にスプレーして毛皮に揉み込みしたところ2週間で改善されました。
【関連記事:愛犬のアレルギー肌が改善!?私が「ひば油」を使う5つの理由】
https://nikomarumama.com/allergie-hibayu/
手作り野菜スープで食事を改善!

以前は市販のドッグフードが中心だった「にこまる」ですが、現在は全ての食事を「手作り野菜スープ」にしています。
手作り野菜スープにアマニ油を数滴入れたところ、効果を感じるようになりました。
アマニ油のオメガ3は、犬の体では作り出せない貴重な栄養素。
血液をサラサラにするので、健康維持や老化防止などにも良いと言われてます。
また炎症を抑えるはたらきがあるので、アレルギーや皮膚の炎症などにも効果が期待できます。
「にこまる」のために野菜スープを作ったり、ひば油風呂に入れたり…
毎日のケアで、少しでも「にこまる」の痒みや皮膚炎を抑えてあげられたら、と思います。
色々試しながら学んでいますよ!
【関連記事:にこまるママ実践!愛犬のための「手作り野菜スープごはん」とその注意点!】

